2025年1月、アメリカではTikTokが禁止目前と報じられ、クリエイターたちは収入源消失を前に震えていました。ビジネスパートナーとしてのツールは泡のように消えるものなのかも知れません。Later社の調査では、87%のTikTokクリエイターが禁止に懸念を示し、88%が収入減を予想したとされています。
AIツールへの依存も同じです。私も使い慣れたLLMのサブスク解約を経験しましたが作業効率が極端に下がり、結局すぐ元のツールに戻りました。他に選択肢がなかったのです。あなたは「贔屓のAIツールが突然使えなくなったら」と考えたことはありますか?
AIツールが消えても、私たちの仕事や生活は続きます。納期は待ってくれませんし、クライアントも待ってくれません。個人ではコントロールできない現実と、依存と捉えつつ備えていくことについて考えていきます。
AIツールにとってTikTok騒動は「対岸の火事」じゃない?
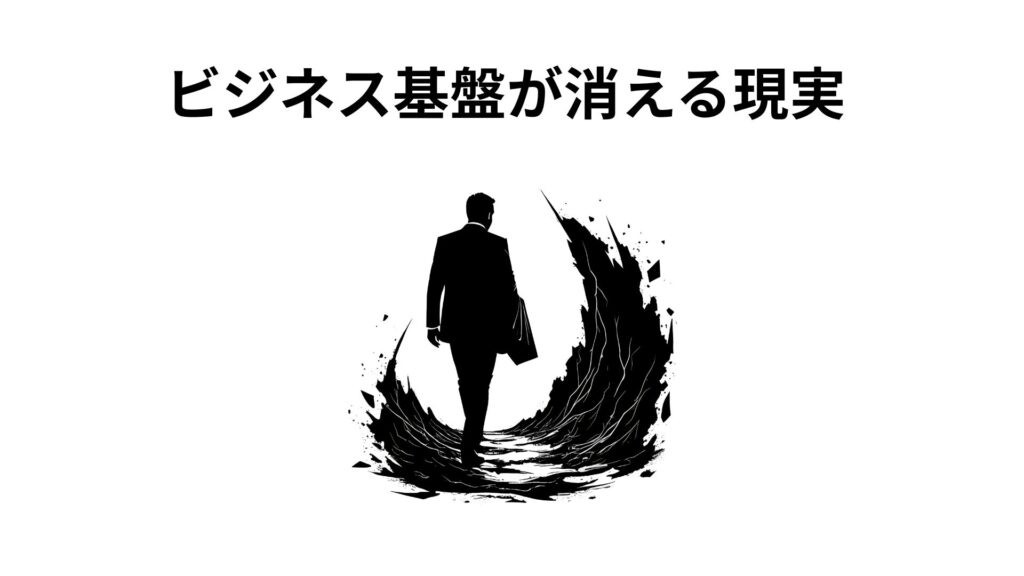
2025年1月19日午前0時を期限に、アメリカでTikTokの利用が禁止される可能性があると広く報じられました。大統領令による譲渡期限が迫る中、クリエイターたちはビジネス基盤の崩壊を覚悟せざるを得なかったのです。
アメリカでのTikTokユーザーは1億7千万人に及び、アメリカ政府はTikTokの米国事業を140億ドル規模と見積もったとの報道もあったようです。
あるエンターテイメント系の若手クリエイターは、当時TikTokに数十万以上のフォロワーを抱えていました。彼は自身の動画を毎日ダウンロードし、Instagram ReelsやYouTube Shortsへの移行準備を進めたといいます。
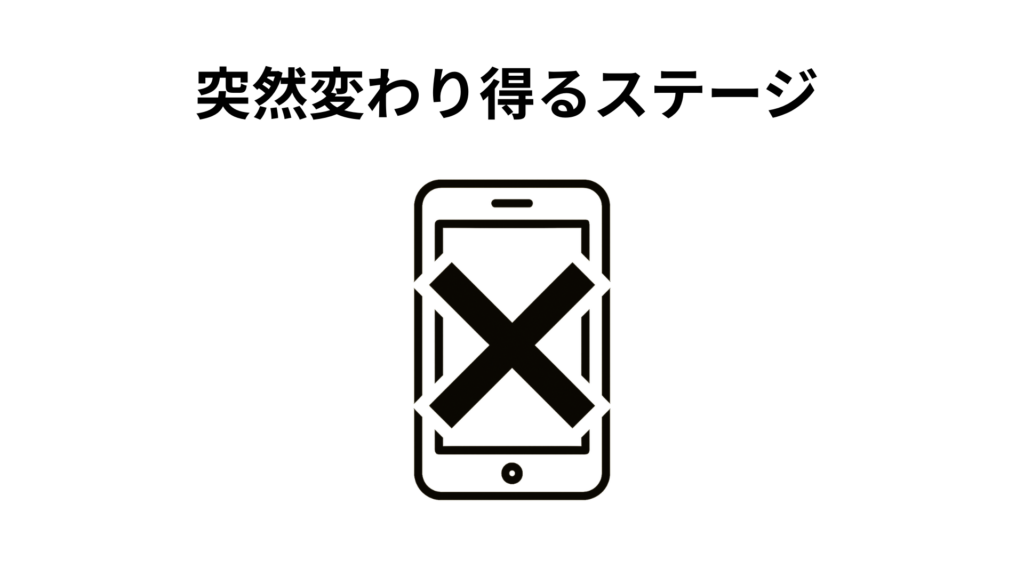
その後、TikTokを巡る動きはOracleを中心とした投資グループへの譲渡交渉が進展したと報じられ、最終的にアメリカ国内でのサービスは継続されました。クリエイターたちは安堵したものの、このとき味わった緊張感は悪夢のように脳裏に焼き付いています。
政府規制はいつでも発動する可能性があり、企業方針の変更も、買収も、突然のサービス終了も、すべて個人ではコントロールできません。「次はAIツールかもしれない」という不安は、TikTok騒動が落ち着きつつある今も残っています。

OpenAI、Anthropic、Google、Metaなど、どの企業も政府規制や企業方針変更のリスクを抱えています。
2024年8月には、Character.AIの共同創業者がGoogleに復帰し、企業構造が突然変化しました。ユーザーには事前通知がなく、個人レベルでは手の打ちようがありません。
2023年2月には、Replikaが政府規制により「恋人モード」を一時削除した結果、多数のユーザーが精神的苦痛を訴えました。Redditで支援リソースが提供される事態にまで発展しています。
OpenAIもChatGPTを頻繁にバージョンアップしており、次のモデルへと進化する中で、挙動が変わり続けています。
TikTok騒動は、AI業界にも同じ「個人ではどうしようもない構造」があると示しました。私たちが依存するツールは、いつでも消えるかもしれないのです。
私たちはAIツールに依存している?
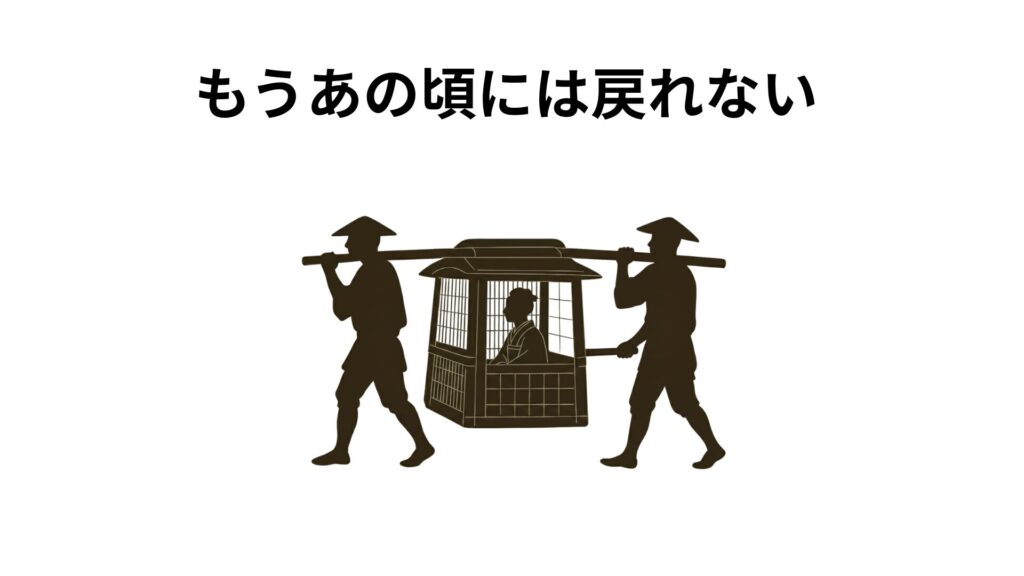
私の場合、LLMがなければ作業効率が落ちると身をもって知りました。でもこれは私だけの話ではないでしょう。多くの職種でAIツールの活用が進んでおり、それぞれの現場で「なくなったら仕事にならない」という状況が生まれています。
エンジニアはコード生成に、例えばGitHub CopilotやCursorを使い、デバッグ時間を削減しています。デザイナーだったらMidjourneyやStable Diffusionで素材を作り、ラフ案の作成時間を短縮するでしょう。マーケターはChatGPTで文章を生成し、コンテンツ制作のスピードを上げています。カスタマーサポートはAIチャットボットで問い合わせ対応を効率化し、人的リソースを削減しています。
これらのツールが突然消えたら、収入源への影響は少なからず発生するはずです。納期に間に合わなくなる可能性も考えられます。「なんとかして今の作業量を確保する」という必要性が、依存に繋がるケースがあるのかも知れません。

ここで重要なのは、依存を否定しないことです。AIはブースターであり、効率化を図ることは現代の必須スキルになりました。AIとの協業で生産性は上がり、収入が増え、時間が生まれます。TikTokクリエイターがTikTokに依存したのは、そこに観客がいて収益が生まれたからであり、私たちがAIツールに依存するのは、それが最も効率的だからです。
しかしいわゆる「プランB」は必要でしょう。贔屓のツールが消えた時にどうするか。完全な代替は困難ですが、何もしないわけにはいきません。依存を認めた上で、備える方法を考える必要があるのです。
贔屓のAIツールが消えた時、本当に耐えられる?

先述したエンタメ系クリエイターがReelsやShortsへ移行したように、LLM(チャット型AI)ユーザーにも選択肢は存在します。代替ツールを模索することは、ビジネスの新たな側面を切り開いてくれるでしょう。「すべてが終わる」と悲観するのは不相応です。
極端な例示ですがChatGPTが消えても、LLM自体は消えず進化を続けます。市場には複数のAI開発企業が肩を並べており、ひとつが消えても次が台頭する仕組みなのであって、焦る必要は無いと断言できます。

まずは複数のツールに少しずつ触れてみるのが一番です。
「ChatGPT、Claude、Gemini、その他にもAIツールってたくさんあるけど、結局何が違うんだろう?」そう思ったことはありませんか。私は最初そのように感じ、実際に色々試すと、返ってくる答えの雰囲気は違っていました。
例えば「取引先へのお礼メールを書いて」と頼んだとします。あるAIツールは丁寧で硬めの文章を返してきますし、別のツールはもう少しフランクな感じです。どちらが良い悪いではなく、性格が違うだけです。
この特性を知っているだけで、贔屓のツールが使えなくなった時の不安が軽くなります。「あっちのツールでもひと手間かければ」という感覚が持てるでしょう。
新しい刺激を求めるイメージで、違うAIツールに無料アカウントを設け、ちょっとだけ試してみると思いのほか楽しめます。「このAIツール優秀だけど、こっち方面では負けるかな」と、試食する感じが良いのでしょう。今日の使い方が、明日の選択肢を広げていきます。
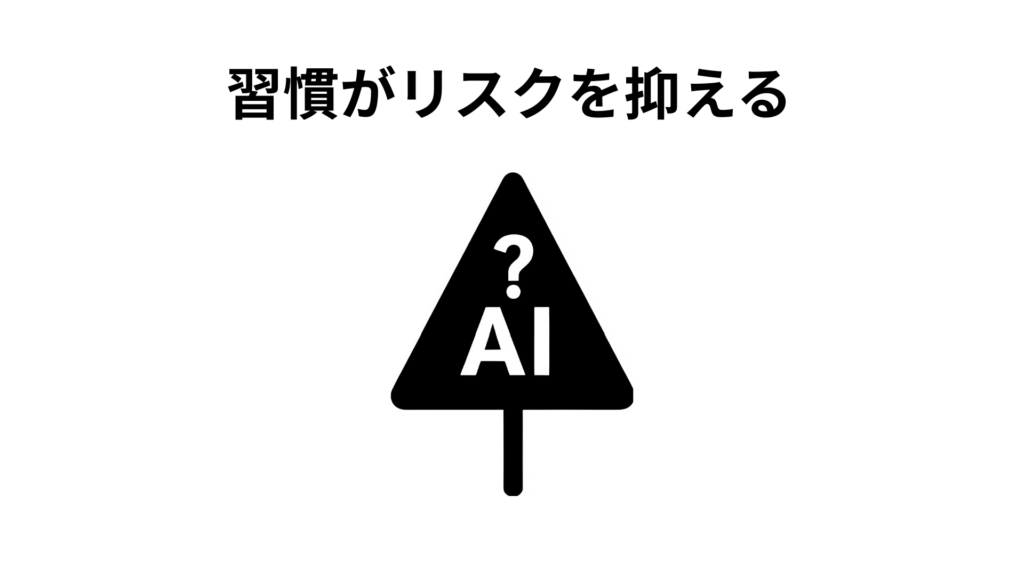
AIに「この商品の評判を教えて」と聞くとどこで仕入れたのか、スパムのような情報をさも事実のように教えることがあります。嘘の情報を作り出すのです。AIは便利ですが、時に自信満々でミスすることがあります。
この事実を知っていると使い方が変わってきます。「AIが言ったから正しい」ではなく「AIが言ったけど本当かな?」と疑う習慣を持つことです。これがあれば、どのツールを使う場合でもリスクを抑えることができます。次に触れるツールは「どんな間違いをしやすい?」と見抜けるようになるでしょう。
経済産業省が2025年3月に公表した「AI事業者ガイドライン」でも、AI利用者は「AIの限界を理解し、過度に依存しないこと」が推奨されています。贔屓にするAIが完璧かどうかなんて、誰も立証できません。一方、他のツールを試してみれば、指先だけでセカンドオピニオンを得られるのですから有益です。
結局のところ、任せれば保証してくれる存在なんて、AIにも人間にも存在しないのかも知れません。
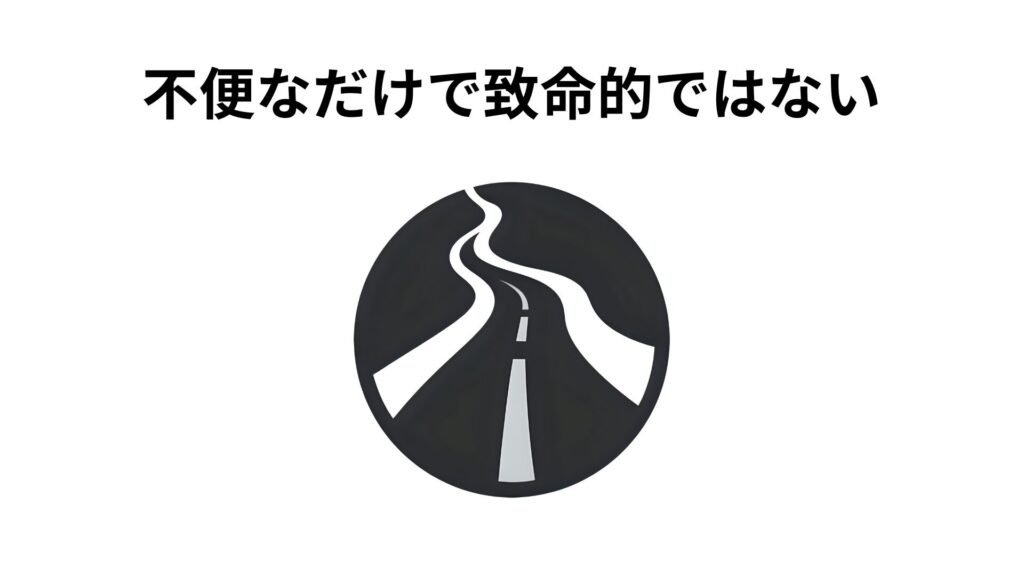
もし本当に贔屓のツールが消えたら不便であることは言うまでもありません。でも不便なだけであり、思い返せばずっと人間の力だけで解決してきたのですから贅沢な悩みでしょう。贔屓のツールをストップして別のツールを使うとなれば、慣れるまではきっとイライラしますが、それは致命的な問題にはなり得ません。
先述のTikTokのエンタメ系クリエイターも、「1年半かけて築いたものを再構築する」と語りました。困難な棘の道かも知れませんがビジネスの岐路で下した決断です。
我々も同じでしょう。そのために今、ちょっとだけ他のツールに触れておく。もしかしたら新たな可能性に繋がるかも知れません。
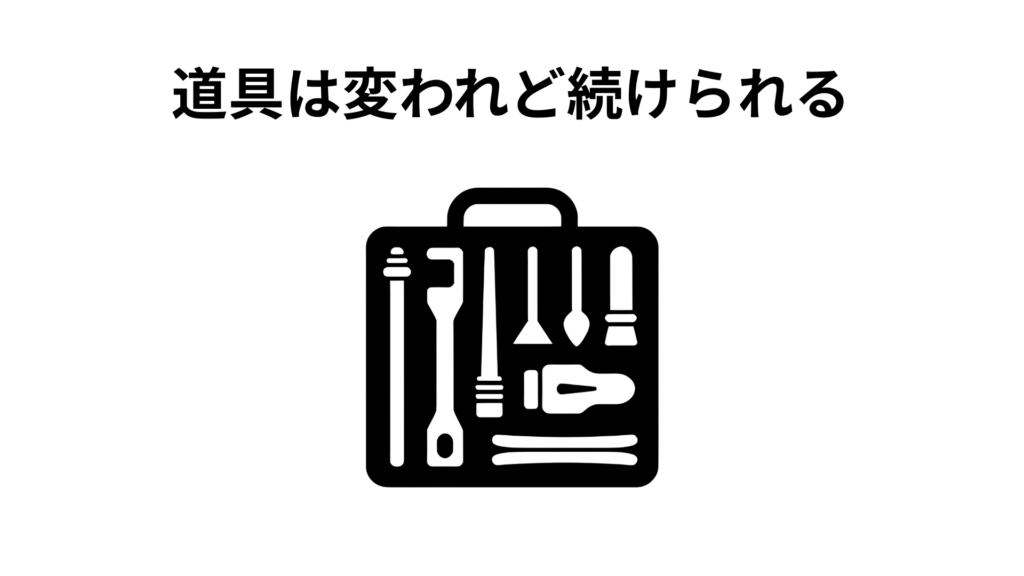
AIは便利な道具です。道具である以上、壊れることもあれば、手に入らなくなることもあります。ちょうどバージョンアップする中に立ち合い、とまどうことがあるかも知れません。でもそれは決して怖がることではなく、道具の寿命、パートナーの昇華と考えるべきでしょう。「指示の仕方にコツあり」、「絶対ではない」あるいは「こういうツールもある」と考える習慣を持っておけば、臨機応変に立ち回ることができます。
それで贔屓のツールが消えた時の不安は、ぐっと小さくなるのではないでしょうか。頼るべき相棒なのだけれども、道具が変わっても続けられる準備を少ししておけば、その積み重ねが備えになるし、優位性を築くはずです。
AIと共に生きるための知恵
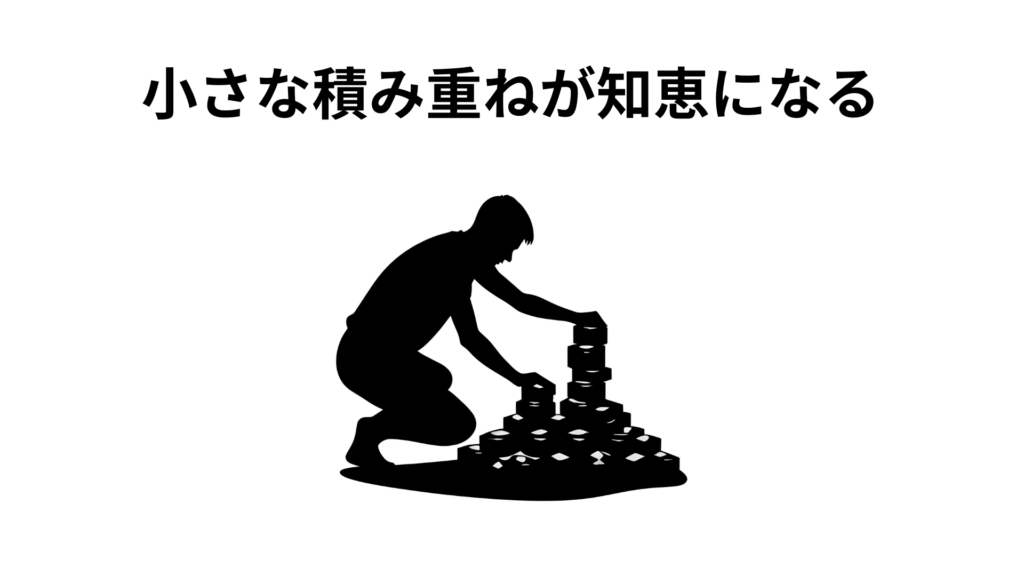
TikTok問題が教えてくれたのは、「待つこと」では何も守れないという事実です。政府規制も企業方針も、私たちにはコントロールできません。贔屓のツールがいつ消えるかも予測できません。この無力感は事実として受け入れるしかないのでしょう。
でも無力だからといって、諦める理由にはなりません。むしろ逆でコントロールできないからこそ、できる範囲に集中してみることに価値があります。週に一度、別のツールを試す。指示の仕方を少し工夫する。出てきた答えを疑ってみる。
これらは小さな行動です。AIツールが消える事態を完全に防げるわけではありません。でもゼロではなく積み重ねであり、その「ゼロではない」を蓄え次の仮説につなげるのが、AI時代を生き抜く知恵かも知れません。
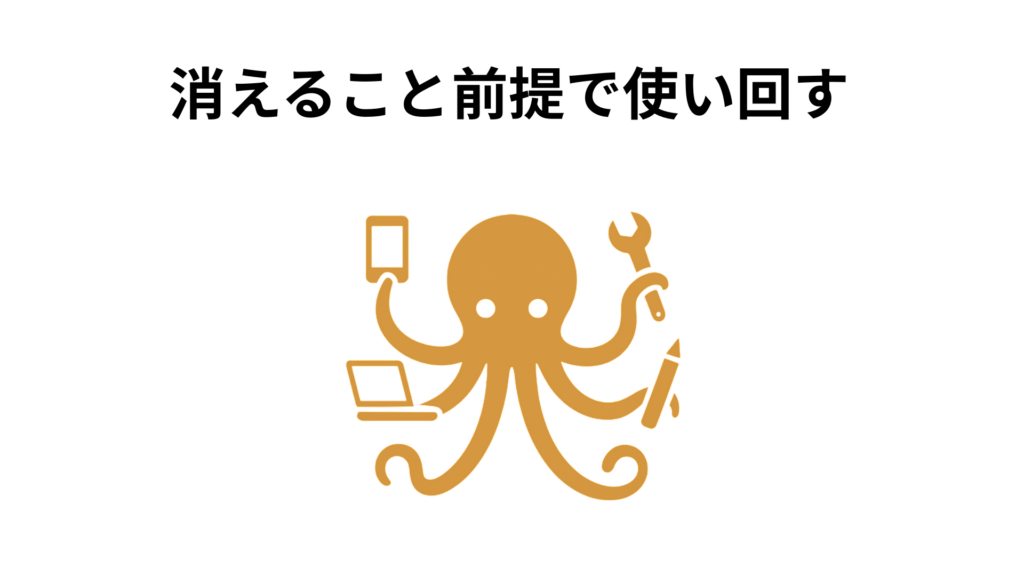
「いつか消える」と考えAIツールを使っていると不安ですが、消えることを前提にしているからこそ、今日を無駄にしない意識につながります。もしサブスクで明日が契約満了日なら、残った時間でできることを色々試すと思うのです。
そして依存していることを認めているからこそ、ツールを最大限に活用できるのでしょう。TikTokクリエイターたちも私たちも同じです。明日消えても今日使えるのであれば、今できることをする。その繰り返しが、結果的に次のツールへの移行力を養っていくのかも知れません。
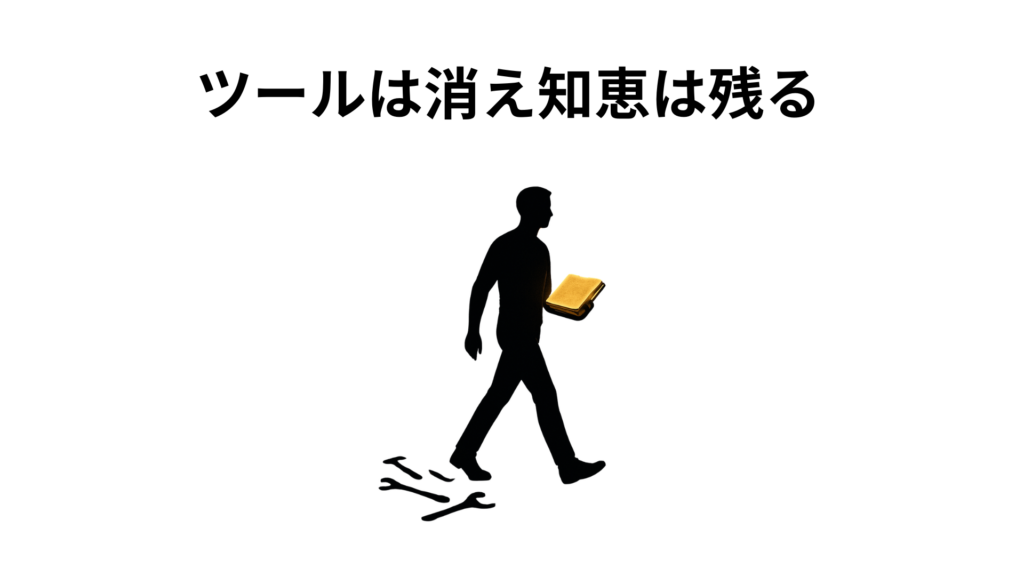
ツールもプラットフォームも消えるし変化します。でも一度身につけた知識は残るものでしょう。
AIへの指示の仕方、間違いの見抜き方、複数ツールの使い分け。こういった知識は、どのAIツールを使う時にも応用できます。自ら時間をかけて試行錯誤しても、効率よく誰かから学んでも、結局いっしょです。大切なのは学び続ける姿勢といって過言はありません。
私もまだ、AIとどう歩むべきかを学んでいる途中で、遠回りし失敗し、前に進んでいます。だからこそ言えるのは、学んだことを分かち合う人が増えるほど、AI時代はより安全で豊かなものになるということです。その循環をつくることこそ、次の時代のリテラシーなのだと思います。
依存しながら備える。矛盾を抱え前に進む。明日ツールが変わっても、今日積み上げた知恵は残ります。それが、AI時代を生きるということだと考えます。
参考データ

Later|What The TikTok Ban Means For Brands & Creators
https://later.com/blog/tiktok-ban/
The White House|Saving TikTok While Protecting National Security
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/saving-tiktok-while-protecting-national-security/
The White House|Fact Sheet: President Donald J. Trump Saves TikTok While Protecting National Security
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/01/fact-sheet-president-donald-j-trump-saves-tiktok-while-protecting-national-security/
Wikipedia|Restrictions on TikTok in the United States
https://en.wikipedia.org/wiki/Restrictions_on_TikTok_in_the_United_States
Ballotpedia|Executive Order: Saving TikTok While Protecting National Security
https://ballotpedia.org/Executive_Order:_Saving_TikTok_While_Protecting_National_Security
Character.AI|Our Next Phase of Growth
https://blog.character.ai/our-next-phase-of-growth/
Wikipedia|Replika
https://en.wikipedia.org/wiki/Replika
経済産業省|AI事業者ガイドライン(第1.1版)本編
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20250328_1.pdf


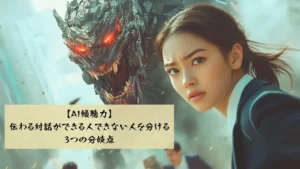







コメント